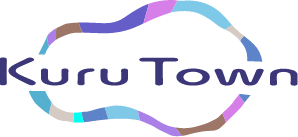車をカスタムする際に、マフラーを交換したいという方は多いのではないでしょうか?車のマフラーは、ただ単に見た目だけの問題ではなくさまざまな役割があります。車検におけるマフラーの基準も年々厳しくなっており、基準を理解していないと車検に通らないことも。
ここでは、マフラーの役割や車検の基準、車検に通らなかった場合の対処法を解説します。
マフラーの役割とは

マフラーは車体の後部から見える筒状のもので、車についている部品を聞かれたときに多くの人が答えられるほど存在感のあるパーツです。
マフラーは、どの車種にも必ず装着されている部品ですが、これはマフラーが重要な役割を担っており、車にとってなくてはならない部品であることを証明しています。
マフラーの役割を、項目別に見ていきましょう。
排気音の低減
車の構造を簡単に説明すると、ガソリンと空気を混合し、爆発させて動く仕組みです。そのため、エンジンから出る排気ガスは高温高圧で、そのまま外へ出してしまうととても大きな音がしてしまいます。
外から見えるマフラーはとても小さなもののように見えますが、マフラーのみを取り外して見てみると、とても大きな部品です。別名「サイレンサー」とも呼ばれるマフラーは、さまざまな構造から成り立っており、この構造を通して排気ガスを排出することで不快感のない音にしています。
エンジンのチューニング
マフラーには、車の加速力に関係するトルクや、エンジンのエネルギー量である出力を決定するチューニングの役割もあります。
装着するマフラーによって、車の乗りやすさや加速時の伸びが変わるので、車をカスタムする際にマフラーを変更する方が多いのです。
有害物質を無害化
マフラーの構造に、キャタライザーと呼ばれる蜂の巣状の触媒が付属しています。キャタライザーの内部には、白金やロジウムなどの貴金属がコーティングされており、排気ガスと貴金属とが化学反応を起こすことで人体や環境にとって有害な物質を無害化しているのです。
車検におけるマフラーの基準

車検に通るマフラーの基準は変更されることが多く、近年ではとくに厳しい基準が設けられています。
車が生産された年代によっても基準は変わりますので、自分の車が車検の基準に適合しているかを把握しておきましょう。
最低地上高
水平な地面に車を置いた状態で、車の最も低い場所までの直線距離を最低地上高と呼びます。
車の最低地上高は、道路運送車両保安基準で9cm以上と定められており、9cm以上確保できていないと車検に通りません。最低地上高9cmというのは、実用する上で車をこすらず走行できる低さです。何もカスタムしていない状態であれば、最低地上高はクリアできています。
よくあるトラブルの例として、車のボディは最低地上高をクリアしているけれど、マフラーが原因で車検に通らなかったというケースがあります。
マフラーは車の底面に装着していますので、マフラー部分も地面から9cm以上距離があるか確認しておきましょう。
車枠及び車体
車枠及び車体は、平成20年12月31日までに生産された車と、平成21年1月1日以降に生産された車とでは基準が変わります。古い年式の車よりも、新しい年式の車のほうが基準が厳しくなっているので注意してください。
まず、平成20年12月31日までに生産された車の基準を解説します。この年代の基準は、マフラーが車のボディから出ていないことと、常識的に考えて交通の妨げにならないことです。
一方、平成21年1月1日以降に生産された車の基準は、フロアラインを含む鉛直面から10mm以上はみ出してはならないとされています。ただし、マフラーの先端に丸みを付けているものを装着し、2.5mm以上の曲率半径を有するものであれば、10mm以上はみ出しても良いとされているのです。
この基準を噛み砕いて解説すると、マフラーは車体からほとんど見えないように装着するか、人や物を傷つけない丸みのあるマフラーにすればOKということになります。
改造マフラーで車検が通るか心配な方は専門業者さんに見積りをもらうと良いでしょう。
近接排気騒音
マフラーが車検に通る基準で、もっとも気にしている方が多いのが、近接排気騒音と呼ばれるマフラーから出る音です。
近接排気騒音も、平成22年3月31日までに生産された車と、平成22年4月1日以降に生産された車とでは基準が変わります。
平成22年3月31日までに生産された車の基準は、騒音を軽減させる消音器が装着されており、近接騒音が普通車で96dB以内、軽自動車の場合は97dB以内であることです。
平成22年4月1日以降に生産された車の基準は、
- 騒音を制御する消音器が付いていること
- 近接排気騒音96dB以下
- 加速騒音が82dB以下であることとなっています。
音の強さを表すdBの基準を身近な音に例えると、電車通過時の高架下が100dB、犬の鳴き声が90dB程度です。
車検に通るマフラーとは

純正品のマフラーは、車検に必ず通るように作られているので問題ありませんが、社外品のマフラーを装着する場合は、車検に通るマフラーを選ばなければなりません。
社外品のマフラーを選ぶ際は、車検対応品やJASMA認定品、保安基準適合品と記載のあるマフラーを購入すると車検に通ります。
車検対応品と保安基準適合品は、文字通り「車検に通るマフラー」であることを表していると容易に判断できますが、JASMA認定品という文字からはどのようなマフラーであるか想像できませんよね。
JASMA認定品のマフラーは、スポーツマフラーの普及を目的に設立された日本自動車スポーツマフラー協会が、車検対応品と保安基準適合品のマフラーよりも厳しい基準で認定しているマフラーです。そのため、この3種類のどれを装着していても、問題なく車検に通ると考えられます。
気をつけなければならないのが、いくら純正品や車検対応品、JASMA認定品、保安基準適合品と記載のあるマフラーであっても、破損や経年劣化による腐食、穴あきで車検に通らない場合もあるということです。
古い車種や、長年同じマフラーを装着しているという場合は、マフラーが傷んでいないかも確認しておきましょう。
マフラーが車検を通らないときの対応

車検を受ける前にできればしっかりとマフラーの状態を確認しておくべきですが、万が一、マフラーに不備が見つかり車検に通らなかった場合の対応をご紹介します。
インナーサイレンサーを装着
マフラーから出る音が原因で車検に通らなかった場合、インナーサイレンサーを取り付ける方法があります。
インナーサイレンサーは、マフラーの内部、出口付近に取り付ける部品で、排気音を逃し音量を下げてくれるものです。
インナーサイレンサーの取り付けはDIYでもできますが、取り付け方に不備があると安全性を損なう恐れがあるため、車検に通らない可能性も出てきます。
取り付けの際は、安全性を損なうことがないよう十分に配慮し、あくまでも補助的なパーツであることを念頭に置いておくようにしましょう。
構造変更申請
マフラーのはみ出しが原因で車検に通らない場合は、構造変更申請を検討してみましょう。構造変更申請とは、基準の範囲内で車の大きさや排気量を変更するための申請です。
しかし構造変更申請をする場合は、申請に必要な書類を集めて、運輸支局へ出向き手続きする必要があります。
マフラーの交換
マフラーが劣化している場合や車検に通らない場合は、車検に通る新しいマフラーに交換するのが一番手っ取り早く、確実です。
しかし新しいマフラーに交換する場合、マフラー自体の値段が約30,000円から100,000円、それに加え工賃も発生しますので、大きな出費となってしまいます。
改造マフラーで車検が通るか心配な方は専門業者さんに見積りをもらうと良いでしょう。
車の年式が古い場合は、マフラーの交換をせず、新しい車に乗り換えるほうがお得な場合もありますので、一度検討してみてください。
まとめ
マフラーは、車のカスタムパーツの中でも人気の部品ですが、近年マフラーにおける車検の基準も厳しくなっています。車検や安全のことを考慮してマフラーを選ぶことが重要です。