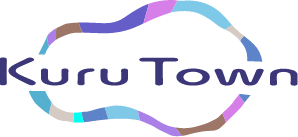車検の有効期限は、車検証やバックミラーの後ろあたりに貼る検査標章に書いてあります。ディーラーで購入した車であれば、事前に案内をしてくれるでしょう。それでも忘れて、車検の有効期限に間に合わないドライバーは少なくありません。もし車検が切れたら、あるいは直前で有効期限に気づいたら、どうすればいいのでしょうか。
車検が切れたらどうなる?再び走らせるには?

車検の有効期限が切れてしまうと、道路運送車両法の第58条により、公道を走らせることができません。もし走らせてしまうと、6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金を科せられます(同第108条)。また、交通違反にもなり6点の減点です。
さらに自賠責保険も切れていると、自動車損害賠償保障法の第5条に違反することになり、1年以下の懲役か50万円以下の罰金を科せられます(同第86条の3)。同じく交通違反にもなって6点の減点です。
トータルすると、最大で1年6ヶ月の懲役か80万円以下の罰金を科せられ、12点減点されます。
車検の有効期限が切れる直前で気づいたなら、当日の23時59分までは有効なので、公道を走らせるのは可能です。急いで車検を受け付けてくれるところに車を運びましょう。ただし、自賠責保険の有効期限が同日である場合は、当日の11時59分までとなります。
それ以上車を移動しなくていいように、整備だけでなく自ら車検もできる「指定工場」へ持ち運ぶのがおすすめです。「認証工場」や「代行業者」、受付だけで整備や車検を提携工場で行うところは、車検を受ける前に有効期限が切れる恐れがあります。
もし気づいた時点で車検の有効期限が切れていたら、そのままでは工場まで持ち運べません。車検が切れている車でも公道を走らせる方法は2種類あります。1つは「仮ナンバー」を取得して運転する方法、もう1つは業者に「積載車」で運んでもらう方法です。
仮ナンバーは市区町村役場の窓口か、運輸支局で発行しています。軽自動車でも同じです。申請に必要なのは車検証と申請期間中に有効な自賠責保険証、運転免許証(本人確認書類)、印鑑(認印でも可)ですが、市区町村によっては不要なものもあります。
手続きにかかる費用は運輸支局なら750円ですが、これも市区町村によってまちまちです。あらかじめ問い合わせたほうが良いでしょう。
仮ナンバーで運行できるのは最大で5日間ですが、車検を受けるために発行するのであれば、自宅から工場まで持ち運べる最短日数となります。また、運転できるのもその2点間を結ぶ合理的な経路に限られており、それ以外のところへ立ち寄ることはできません。
自賠責保険も切れている場合は、保険会社の営業所や代理店で加入できます。最短で加入できるのは1ヶ月分です。その後に車検を受けることを考えると、2年分加入したほうが、お得でしょう。仮ナンバーを申請する前に加入しましょう。
業者に依頼して工場へ運んでもらうには、積載車が必要です。レッカー車を使うなら、仮ナンバーを発行しなければいけません。車輪が接地しているため、公道を走っているとみなされるからです。
積載車を使うのは、業者や運ぶ時間にもよりますが1~2万円くらいかかります。車検を受け付けてくれる業者の中には、仮ナンバーの申請から代行してくれるところもありますが、その分を上乗せして請求されるでしょう。
ほかにもある?直前で車検をするデメリット

有効期限が切れてから車検を受けるのは、工場まで車を運ぶ費用が余分にかかります。直前に気づいて車検を受けるのも、費用面ではデメリットです。
なぜなら、車検を受け付けている業者の多くは、条件を満たすと法定料金以外の費用を割引しています。法定費用とは、自動車重量税や自賠責保険料、検査料などであり、どこの業者も同じ金額です。一方、それ以外の費用とは整備費や工賃、サービス料などで、業者によって異なります。
割引する条件は早期の申し込みや、平日の車検、代車を必要としないなどです。ほかの業者の見積もりより高ければ、割引してくれる業者もあります。
自身の車の状態に合った専門業者を見つけておくと良いかもしれません。
直前に車検を受けると早期割引は適用されませんし、見積もりを取って業者同士を比較する余裕もありませんから、割高な料金で受けるしかないわけです。ただでさえ、車検では部品の交換などで、予想以上の費用が発生します。できるだけ早く準備して、出費を抑えましょう。
ほかにも、直前で車検を受けようとするのはリスクがあります。車検の業者は予約を優先しており、申し込もうとしても空きが無いかもしれません。やっと予約が取れても、それまでに車検や自賠責保険の有効期限が切れる恐れがあります。
また、車検に合格するには、事前に整備して検査項目の不具合を解消しなければいけません。整備する工場によっては、必要な部品の調達に時間がかかる場合もあり、それまでに車検の有効期限が切れる可能性があります。
もし、車検ができない工場なら、運輸支局や軽自動車検査協会まで運ぶために、仮ナンバーを取得したり、積載車を用意したりしなければいけません。指定工場に持ち運ぶのをおすすめするのは、整備の最中に車検の有効期限が切れても、公道を走らせずに車検を受けられるからです。
ただし、指定工場で車検を受けられても、車検証を発行するには運輸支局や軽自動車検査協会で手続きしなければいけないため、それまで公道を運転するのは待たされます。
ユーザー車検なら、工場に持ち込まなくても自分で点検して車検を受けられますが、合格しなければその箇所を整備した上で、再度受けなければいけません。結局は仮ナンバーや積載車が必要になります。こうした事態を防ぐためにも、車検は余裕を持って受けたいところです。
車検はいつからできるの?

車検は有効期限にかかわらず、いつでも受けられます。極端な話、車検を受けた翌日に受けても構わないわけです。ただし、次の有効期限は車検を受けた日の2年後(自家用乗用車、軽乗用車の場合)になってしまい、金額を考えると大損です。
有効期限が前倒しにならず、きっかり初回なら3年、2回目以降なら2年になるのは、1ヶ月前からです(離島は2ヶ月前)。例えば5月10日が有効期限なら、4月10日以降に受ければ、次の有効期限が前倒しになりません。
有効期限が3月29日であれば、うるう年に限り2月29日が1ヶ月前になりますが、それ以外は2月28日です。また、30日や31日など、前月に該当する日付がないときは末日が有効期限になります(例:10月31日→9月30日)。
もっとも、それは運輸支局や軽自動車検査協会で車検を受ける場合で、指定工場ではさらに15日前から有効期限を前倒しせずに車検を受けられます。
なぜなら、先述のとおり指定工場でも、車検証を発行するには運輸支局や軽自動車検査協会で手続きしなければいけません。その期限が検査に合格してから15日以内だからです。
車検の有効期限は、冒頭で述べたとおり、車検証や検査標章で確認できます。ほかにも、車を購入したディーラーから案内が来るかもしれません。また、新車で購入した場合は、任意保険の更新時期が車検と重なるケースが多いようです。
直前になって慌てないように、時々は車検証を見るなどして、有効期限を確認しましょう。
また見積もりやサービスなどを比較して専門業者を事前に選んでおくのも余裕につながります。
まとめ
車検の有効期限に間に合わないときは、仮ナンバーを発行したり、積載車を利用したりすると、車検を受けられる工場まで運べます。そのまま運転するのは道路運送車両法違反です。
車検は有効期限の1ヶ月前(指定工場であればさらに15日前)からなら、次の有効期限が前倒しになりません。早めに受けると早割が適用されたり、見積もりを比較して安く車検を受けられる業者を見つけられるなど、お得になります。