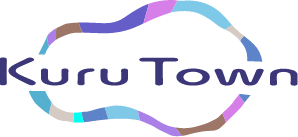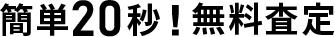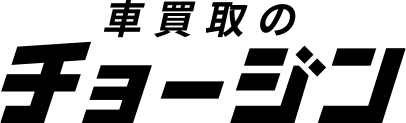
山形県の



山形県の中古車買取・売却でチョージンが選ばれる理由
-
選ばれる理由1
膨大な販路があるから最高値での買取が可能!
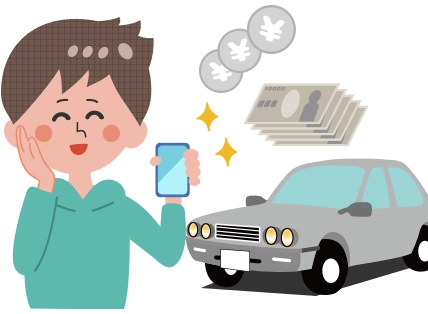 チョージンでは、無料査定は24時間いつでも受付を行っています。15,000社以上の豊富な販路を駆使して、最高値での買取を行います。
チョージンでは、無料査定は24時間いつでも受付を行っています。15,000社以上の豊富な販路を駆使して、最高値での買取を行います。
リアルタイムで最高値を提示するため、一本のお電話で査定額をすぐに確認することが可能です。また、書類手続きからお車の引き取りまで全て無料でサポート致します。 -
選ばれる理由2
従来の査定基準より高値の査定が期待できる!
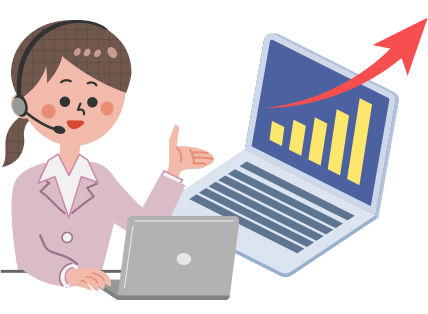 チョージンは通常の査定基準にとどまらず、海外での販売網を活かし、高額な買取を実現しています。日本車は国内外で高い人気があり、お車の高価買取が可能です。また、各メーカーや車種についての豊富な知識を持ち、一般的な中古車市場の相場を上回る査定実績もあります。あなたの大切な車には、まだまだ高い価値があるかもしれません。
チョージンは通常の査定基準にとどまらず、海外での販売網を活かし、高額な買取を実現しています。日本車は国内外で高い人気があり、お車の高価買取が可能です。また、各メーカーや車種についての豊富な知識を持ち、一般的な中古車市場の相場を上回る査定実績もあります。あなたの大切な車には、まだまだ高い価値があるかもしれません。 -
選ばれる理由3
豊富な経験と実績のあるカスタマーサポート!
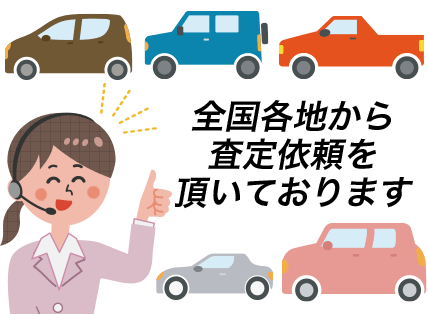 チョージンのカスタマーサポートは、中古車の買取に関する疑問や不安を迅速に対応します。適切な査定額の提供から書類手続きやお車の引き取りまで、豊富な経験を持つカスタマーサポートが親身で丁寧な対応をご提供いたします。お客様の安心と満足を第一に考えており、いつでもお力になります。
チョージンのカスタマーサポートは、中古車の買取に関する疑問や不安を迅速に対応します。適切な査定額の提供から書類手続きやお車の引き取りまで、豊富な経験を持つカスタマーサポートが親身で丁寧な対応をご提供いたします。お客様の安心と満足を第一に考えており、いつでもお力になります。
山形県の中古車買取ランキング(車種編)
全ての車種の買取情報を調べる山形県の買取・査定実績
-
- 日産 フェアレディZ フェアレディZ
- 山形県酒田市
- 2004年式/70,000km/3,500cc
- 買取価格:150,000円
-
- トヨタ イプサム イプサム Lセレクション
- 山形県山形市
- 1997年式/154,000km/2,000cc
- 買取価格:150,000円
-
- スズキ スイフトスポーツ スポーツ ディスチャージヘッドランプ装着車
- 山形県酒田市
- 2012年式/172,000km/1,600cc
- 買取価格:65,000円
-
- スズキ パレット X
- 山形県酒田市
- 2008年式/92,000km/660cc
- 買取価格:15,000円
-
- トヨタ マークX
- 山形県東置賜郡高畠町
- 2006年式/130,000km/2,500cc
- 買取価格:60,000円
-
- BMW 118i プレイ
- 山形県酒田市
- 2023年式/7,000km/1,500cc
- 買取価格:2,400,000円
-
- トヨタ ハリアー エレガンス GRスポーツ
- 山形県天童市
- 2019年式/3,800km/2,000cc
- 買取価格:2,200,000円
-
- トヨタ アルファード SA
- 山形県山形市
- 2015年式/76,000km/3,500cc
- 買取価格:2,000,000円
-
- トヨタ タンドラ Wキャブ リミテッド
- 山形県寒河江市
- 2014年式/95,000km/5,660cc
- 買取価格:1,280,000円
-
- ダイハツ コペン GRスポーツ
- 山形県天童市
- 2019年式/35,000km/660cc
- 買取価格:1,150,000円
-
- トヨタ プリウス Aプレミアム ツーリングセレクション
- 山形県西置賜郡飯豊町
- 2016年式/66,000km/1,800cc
- 買取価格:1,100,000円
-
- 日産 デイズ ハイウェイスターX
- 山形県西村山郡河北町
- 2021年式/13,000km/660cc
- 買取価格:910,000円
-
- ホンダ アクティトラック SDX
- 山形県東置賜郡川西町
- 2021年式/1,310km/660cc
- 買取価格:900,000円
-
- マツダ RX-7 【限定車】Type R BATHURST X
- 山形県西置賜郡飯豊町
- 1995年式/110,000km/1,300cc
- 買取価格:770,000円
-
- スズキ スペーシア カスタム Z ターボ
- 山形県最上郡金山町
- 2017年式/27,000km/660cc
- 買取価格:630,000円
-
- BMW X6 xDrive35i
- 山形県東根市
- 2011年式/走行距離不明/排気量不明
- 買取価格:615,000円
-
- トヨタ MR2 GT
- 山形県酒田市
- 1996年式/178,000km/2,000cc
- 買取価格:550,000円
-
- トヨタ ハイラックスサーフ SSR-X
- 山形県鶴岡市
- 1996年式/255,000km/3,000cc
- 買取価格:530,000円
-
- レクサス CT200h 標準
- 山形県鶴岡市
- 2016年式/160,000km/1,800cc
- 買取価格:510,000円
-
- ダイハツ ハイゼットトラック ジャンボ“SAⅢt”
- 山形県上山市
- 2018年式/28,900km/660cc
- 買取価格:500,000円
-
- プジョー 508SW SW GTブルーHDi
- 山形県上山市
- 2019年式/16,000km/2,000cc
- 買取価格:450,000円
-
- トヨタ C-HR G
- 山形県山形市
- 2017年式/125,000km/1,800cc
- 買取価格:450,000円
-
- トヨタ アクア X URBAN ソリッド
- 山形県東置賜郡川西町
- 2015年式/74,000km/1,500cc
- 買取価格:450,000円
-
- トヨタ プリウスα S
- 山形県米沢市
- 2012年式/60,000km/1,800cc
- 買取価格:420,000円
-
- レクサス HS250h バージョンC
- 山形県寒河江市
- 2014年式/128,095km/2,360cc
- 買取価格:420,000円
-
- いすゞ エルフ
- 山形県飽海郡遊佐町
- 1995年式/500,000km/4,330cc
- 買取価格:415,000円
-
- トヨタ プリウス S
- 山形県天童市
- 2013年式/61,000km/1,800cc
- 買取価格:410,000円
-
- トヨタ ウィッシュ 1.8A
- 山形県山形市
- 2014年式/90,000km/1,800cc
- 買取価格:400,000円
-
- アウディ A1 TSFI
- 山形県酒田市
- 2013年式/48,000km/1,400cc
- 買取価格:350,000円
-
- マツダ CX-5 20S
- 山形県西村山郡河北町
- 2013年式/107,650km/2,000cc
- 買取価格:350,000円
 山形県で買取強化中の車種査定額最高30%UP↑
山形県で買取強化中の車種査定額最高30%UP↑
セダン車の高価買取り強化車種
(2024年10月時点)
-

トヨタ プリウス
前月比査定額30%UP!
査定を申し込む -

日産 スカイライン
前月比査定額30%UP!
査定を申し込む -

トヨタ クラウンハイブリッド
前月比査定額20%UP!
査定を申し込む -

スバル WRX S4
前月比査定額10%UP!
査定を申し込む -

トヨタ カムリ
前月比査定額10%UP!
査定を申し込む
ワンボックス車の高価買取り強化車種
(2024年10月時点)
-

トヨタ アルファード
前月比査定額30%UP!
査定を申し込む -

トヨタ ヴェルファイア
前月比査定額30%UP!
査定を申し込む -

トヨタ ヴォクシー
前月比査定額20%UP!
査定を申し込む -

三菱 デリカD:5
前月比査定額10%UP!
査定を申し込む -

トヨタ ハイエースワゴン
前月比査定額10%UP!
査定を申し込む
SUV車の高価買取り強化車種
(2024年10月時点)
-

トヨタ ランドクルーザープラド
前月比査定額30%UP!
査定を申し込む -

トヨタ ランドクルーザー
前月比査定額30%UP!
査定を申し込む -

トヨタ FJクルーザー
前月比査定額20%UP!
査定を申し込む -

ジープ ラングラー
前月比査定額15%UP!
査定を申し込む -

トヨタ ハリアー
前月比査定額10%UP!
査定を申し込む
軽自動車の高価買取り強化車種
(2024年10月時点)
山形県の市町村から車買取情報を探す
山形県でチョージンの中古車買取をご利用頂いたお客様の声
山形県で実際にお車を売却いただいたお客様の声・口コミをご紹介いたします。
総合満足度
5.0
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
初めて利用しましたが、問い合わせした時の対応も良く満足出来ました。ログインして進歩状況を確認出来るので安心感もありました。ありがとうございました。
総合満足度
5.0
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
問い合わせの登録をして、すぐに連絡がきた。対応の速さに余程買い取り価格に違いがない限り御社にお願いしようと即決した。
総合満足度
4.0
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
電話だけの情報だけで、価格か決まった。その後に御社から車の写真を送るように連絡があった。小生の車は20年落ちだが、デーラー車検で、かつオイル、ATオイル、タイミングBT、等定期交換、ヘッドランプ交換等交換で見た目が、綺麗でした。あと御社の手続き、振り込みがスピーディーで、とても良いです。
山形県の車買取でよくあるご質問
山形県で車査定を依頼したいのですが、対象外となる地域はありますか?
チョージンは山形県全域を対象で車買取りを行っております。出張査定は無料ですのでご安心下さい。
車売却の契約後の引渡しは山形県のどちらかに持ち込まなければなりませんか?
車売却のご契約後はご自宅まで車の引取りにお伺い致します。山形県全域で車の引取り料は無料ですのでご安心ください。
車検証に山形県以外の住所が記載されています。必要書類を教えてください。
車検証記載の住所が現住所と異なる場合は住民票が必要となります。詳しくはチョージンまでお問い合わせください。
住所変更の必要書類
廃車手続きの必要書類
無料査定フォームから依頼した後、どの位で連絡がきますか?
無料査定のご依頼を頂いた後、おおむね10分以内にご連絡させて頂きます。
チョージン車買取と一括査定との違いは?
一括査定は複数社(サービスによっては最大10社)にフォームに入力した内容が一括送信されるため、複数社から一斉に電話がかかってきたり、同じ内容を聞かれたりして煩わしいと思う方も多いと聞きます。
チョージン車買取サービスは、一社だけとのやりとりになりますので、煩わしい思いをすることなく査定を受ける事ができます。
ローン中の車でも売却できますか?
残債が残っているお車でも売却できますが、原則として全額の残債をお支払いただく必要があります。また所有者であるディーラーやローン会社との所有権解除の書類のやり取りを行うことでお車の売却が可能です。詳しくはチョージンのスタッフへお気軽にご相談ください。
【ローン返済中の車売却】残債があっても車を買い取ってもらう方法
山形県の運輸支局
| 運輸支局 | 管轄 | 対応地域 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 山形運輸支局 |
|
山形市、米沢市、新庄市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市、南陽市、東村山郡、西村山郡、北村山郡、最上郡、東置賜郡、西置賜郡 | 〒990-2161 山形県山形市大字漆山字行段1422-1 |
050-5540-2013 |
| 庄内自動車検査登録事務所 |
|
鶴岡市、酒田市、東田川郡、飽海郡 | 〒997-1321 山形県東田川郡三川町大字押切新田字歌枕3 |
050-5540-2014 |
山形県の軽自動車検査協会
| 軽自動車検査協会 | 管轄 | 対応地域 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 山形事務所 |
|
山形市、米沢市、天童市、南陽市、新庄市、長井市、上山市、尾花沢市、東根市、村山市、寒河江市、最上郡、北村山郡、東村山郡、西村山郡、東置賜郡、西置賜郡 | 〒990-2251 山形県山形市立谷川3-3553 |
050-3816-1835 |
| 山形事務所 庄内支所 |
|
鶴岡市、酒田市、東田川郡、飽海郡 | 〒997-1321 山形県東田川郡三川町大字押切新田字歌枕109-3 |
050-3816-1836 |
山形県の自動車税に関するお問い合わせ
| 名称 | 管轄区域 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 村山総合支庁 | 山形市、上山市、天童市、山辺町、中山町 | 〒990-2492 山形県山形市鉄砲町二丁目19-68 |
023-621-8139 |
| 村山総合支庁 納税課 | 村山市、東根市、尾花沢市、大石田町 | 〒995-0024 山形県村山市楯岡笛田四丁目5-1 |
0237-47-8621 |
| 最上総合支庁 税務課 | 新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村 | 〒996-0002 山形県新庄市金沢字大道上2034 |
0233-29-1226 |
| 置賜総合支庁 税務課 | 米沢市、南陽市、高畠町川西町 | 〒992-0012 山形県米沢市金池七丁目1-50 |
0238-26-6013 |
| 庄内総合支庁 税務課 | 鶴岡市、酒田市、庄内町、三川町、遊佐町 | 〒997-1392 山形県東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 |
0235-66-5422 |
山形県でのチョージンの車買取の流れ
-

Webフォームで無料査定
Webフォームの入力はたったの20秒で完了。対象エリアは山形県全域です。
-

ご連絡
フォームでご入力頂いたお電話番号にチョージンの提携店よりご連絡させて頂きます
-

ご契約
チョージン車買取は実車査定は無く、お電話にて査定額をお伝えします。査定額に納得頂けた場合、ご契約の流れとなります。
-

車のお引取り・お支払い
山形県全域を対象として車の引取りにお伺いします(無料)。当日には必要書類をお預かりし、その後速やかに買取価格をお振込み致します。
✕
- ステップ1メーカー
- ステップ2車種
- 任意年式
- 任意走行距離
国産車
- トヨタ
- 日産
- スズキ
- ダイハツ
- ホンダ
- マツダ
- スバル
- 三菱
- いすゞ
- 日野
- レクサス
- 三菱ふそう
- 光岡
輸入車
- メルセデス・ベンツ
- BMW
- フォルクスワーゲン
- アウディ
- MINI
- ボルボ
- UDトラックス
- ジープ
- プジョー
- ルノー
- ポルシェ
- フィアット
- スマート
- ランドローバー
- シトロエン
- ジャガー
- アバルト
- アルファロメオ
- マセラティ
- シボレー
- フェラーリ
- キャデラック
- フォード
- ランボルギーニ
- ベントレー
- ダッジ
- アストンマーチン
- ロールス・ロイス
- アルピナ
- クライスラー
- ロータス
- ヒュンダイ
- GMC
- ローバー
- ランチア
- MG
- ポンティアック
- ビュイック
- サーブ
- ハマー
- オペル
- リンカーン
- サターン
- AMG
- デイムラー
- マーキュリー
- その他・不明
- もっと古い・分からない
- 令和6年(2024年)
- 令和5年(2023年)
- 令和4年(2022年)
- 令和3年(2021年)
- 令和2年(2020年)
- 平成31年/令和1年(2019年)
- 平成30年(2018年)
- 平成29年(2017年)
- 平成28年(2016年)
- 平成27年(2015年)
- 平成26年(2014年)
- 平成25年(2013年)
- 平成24年(2012年)
- 平成23年(2011年)
- 平成22年(2010年)
- 平成21年(2009年)
- 平成20年(2008年)
- 平成19年(2007年)
- 平成18年(2006年)
- 平成17年(2005年)
- 平成16年(2004年)
- 平成15年(2003年)
- 平成14年(2002年)
- 平成13年(2001年)
- 平成12年(2000年)
- 平成11年(1999年)
- 平成10年(1998年)
- 平成9年(1997年)
- 平成8年(1996年)
- 平成7年(1995年)
- 平成6年(1994年)
- 不明・分からない
- 0km~10000km
- 10,001km~20,000km
- 20,001km~30,000km
- 30,001km~40,000km
- 40,001km~50,000km
- 50,001km~60,000km
- 60,001km~70,000km
- 70,001km~80,000km
- 80,001km~90,000km
- 90,001km~100,000km
- 100,001km~110,000km
- 110,001km~120,000km
- 120,001km~130,000km
- 130,001km~140,000km
- 140,001km~150,000km
- 150,001km~160,000km
- 160,001km~170,000km
- 170,001km~180,000km
- 180,001km~190,000km
- 190,001km~200,000km
- 20万km超え